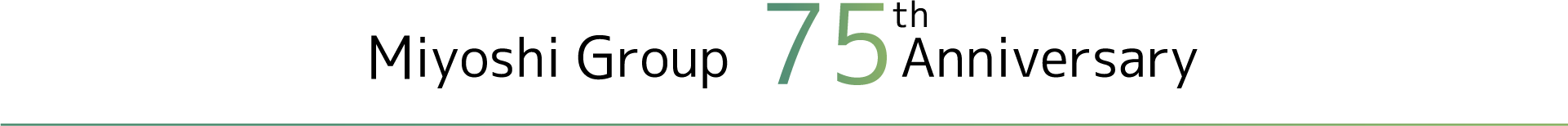
アスター
アスター(Callistephus chinensis(L.)Nees)は中国大陸東北部原産のキク科の一年草で別名エゾギクとも呼ばれています。従来は、高温期に咲く、水揚げの良い盆の仏花として栽培されていましたが、近年、改良された新しい花色、多様な花型を持つ品種が次々と登場しており、アレンジメントにも用いられるようになってきました。

アレンジメントにも使える品種開発・導入
ミヨシのアスター育種は1949年の創業と同時に始まりました。当初は外部育種家の品種導入が中心でしたが、1984年の「コマシリーズ」発表を機に自社育種へと転換しました。マーガレットのような雰囲気を持つ一重咲きの「コマシリーズ」は、それまでの仏花用アスターのイメージを覆し、アレンジメントフラワー素材としての可能性を示しました。

この成功を機に、アレンジメントフラワー用として小輪多花性の「ヒメシリーズ」、八重咲きの「プチシリーズ」、一重咲きの「ハナシリーズ」と、次々に画期的な品種を開発。ピンチ栽培という新たな採花スタイルも確立し、「アスターと言えばミヨシ」という評価を築き上げました。

「マカロンシリーズ」の開発
現在の主力品種の一つ、「マカロンシリーズ」は2016年から展開されている小輪ポンポン咲き品種です。耐病性と早生性を目標に開発されました。現在7色展開され、愛らしいフォルムで人気を博しています。
大輪咲きの導入
もう一つの主力シリーズである大輪咲き品種「ボブシリーズ」と「マッシュシリーズ」は、海外育種会社から導入された「洋花のアスター」です。当初は栽培マニュアルもなく、電照時間や適作型の確立に苦労しましたが、産地との協力により栽培方法(周年電照ハウス栽培)を確立しました。ニュアンスカラーやスプレー咲き、スタンダード仕立てなど、従来のアスターにはない特徴が市場で高く評価されています。特に「マッシュラベンダー」は、その魅力的な花型と花色で大輪アスター普及の牽引役となりました。

安定的な種子生産を目指して
かつては国内委託生産が中心でしたが、現在は高齢化とコスト高から中国での委託生産へと移行しています。1998年から試験採種を開始し、2000年からは本格的に中国での採種がスタート。委託先との良好な関係を築きながら、高品質な種子の安定供給を実現しています。
