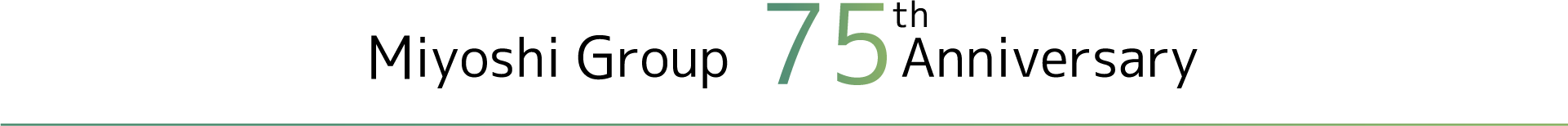
ユーストマ
ユーストマは、日本における育種の歴史が長く、現在流通している品種の大半が日本育成です。ミヨシグループにおいても、1991年の「ネイルシリーズ」発表を皮切りに、2015年には「ボレロホワイト」、2017年には「ハピネスホワイト」を発表するなど、自社育成ユーストマの育種・開発・販売を牽引してきました。これらの品種は、国内のみならず海外にも販路を拡大し、ミヨシのユーストマはグローバルに成長を遂げました。現在、ユーストマは育種競争が激化し、形質だけでなく耐病性や栽培特性に優れた品種が求められています。

ユーストマの育種の歴史
ユーストマ販売のはじまり 〜固定種の時代〜
ミヨシは創業初期から個人育種家からユーストマを導入し、販売を開始しました。1950年代から1980年代は、白や紫、桃色を中心とした単色の一重咲き品種が主流でした。1986年に発表した「スカイフレンド」「レディフレンド」は初の覆色品種で、プラグ苗限定での販売という当時としては先進的な取り組みと相まって、爆発的なヒットとなりました。育苗が難しいユーストマをプラグ苗で供給することで、その後の品種普及に大きく貢献しました。
八ケ岳農場での育種のはじまり 〜 F1品種発表〜
1986年、ミヨシは八ケ岳農場でユーストマのF1育種に着手しました。高品質で安定した品種を目指して育種を進め、1991年に「ネイルシリーズ」を発表しました。その後、1990年代には早生品種の「キャンディシリーズ」、晩生品種の「マイテシリーズ」「エクセルシリーズ」など、一重咲き品種を発表し、品種のバラエティが拡充しました。これにより周年流通が可能となり、ユーストマの重要性が高まりました。

ユーストマ育種の転換期 〜一重咲きから八重咲きへ〜
1990年後半から2000年初頭は、ユーストマの花型が一重咲きから八重咲きへと移行する転換期でした。当時、サカタ社の品種が高いシェアを誇っていましたが、ミヨシは他社品種のネガティブな要素を克服する品種の開発を目指しました。生産農家と連携し、意見を聞きながら品種開発を進めていきました。
「ボレロホワイト」の開発
2003年の交配から生まれた「ボレロホワイト」は、2004年から試作され、暖地での栽培や冬期の安定出荷が可能な品種として評価されました。豪華な花型ではなく丸弁のノーマル咲きでしたが、安定した出荷率の高さから「高収益性品種」として認知され、国内流通量No.1の白八重品種となりました。

「ハピネスホワイト」の開発
2000年代後半、ユーストマ業界は「フリル・フリンジ咲き」で「一茎一花」の大輪品種が流通するなど、高級化の傾向が強まりました。しかし、既存の「フリル・フリンジ咲き」品種は栽培が難しく、色の安定性にも課題がありました。ミヨシは「いつでも・どこでも・だれにでも作れる純白フリル品種」を目標に開発を進め、「ハピネスホワイト」を作出しました。本品種は、2013年から各地で試作され、栽培環境に左右されにくい特性が評価されました。同年、第59回全日本花卉品種審査会にて「農林水産大臣賞」を受賞し、高冷地での夏秋栽培に適した品種として大ヒットとなりました。

ピンク品種の育種へ 〜モアナシリーズ、チアシリーズ〜
2010年頃からピンク八重品種の需要が高まり、ミヨシはピンク親系統を一新するため、ユーストマ用の育種ハウスを新設しました。「抜け感のある緑芯ピンク八重」で、「濃淡ピンク」の「通常咲とフリル咲」の品種を目標に掲げ、育種を進めました。2020年には「モアナシリーズ」、2021年には「チアシリーズ」を発表し、普及を進めました。

アレンジメント
ノアシルキーピンクの登場
生産者からの「ライトピンクのハピネス」の要望に応えるため、フリンジタイプのライトピンク品種の育種を始めました。試行錯誤の末、「ノアシルキーピンク」を作出しました。当初、色が薄いという懸念もありましたが、花持ちの良さや花型の安定感、日本人に好まれるライトピンクの発色から、新たなカテゴリの品種になると確信しました。国内外で評価を高めている本品種は、海外でのさらなる売上向上も期待されています。

