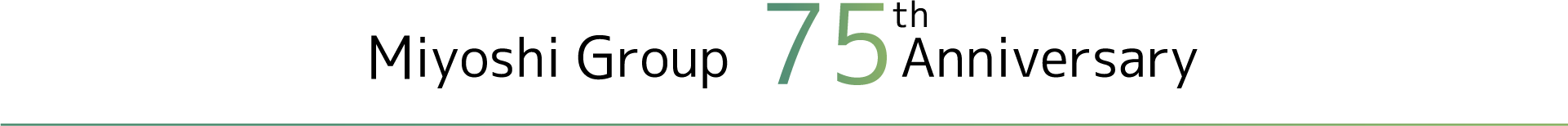
リモニウム
(スターチス)
1970年代、洋花ブームに乗って、シニュアタ・アルタイカ・カスピア・ラティフォリアなどの実生苗によるリモニウムの切り花栽培が増加しました。1980年代には、組織培養による苗生産がミヨシを皮切りに始まり、均一な苗の供給が可能になるとともに、シニュアタ、宿根性ハイブリッドスターチスの育種が日本で大きく進歩しました。1990年代にはミヨシは暖地促成栽培を実現する高冷地育苗による供給体制を整え、産地の期待に応えることになりました。

宿根スターチスから始まった品種開発
三好靱男は、創業期よりスターチスを新しい花材として世に広めることを念願として、様々な原種の輸入種子の販売を始め、1979年にはペレジーの、1980年にはアルタイカの組織培養による苗の生産販売を開始しました。1979年のペレジーの組織培養苗の販売はスターチスでは日本初とされています。その後も導入・開発を積極的にすすめ、1987年に発売開始したハイブリッド種である「サンピエール」「ベルトラード」は、海外市場を席巻するヒット商品となりました。

シニュアタの国内トップサプライヤー
リモニウムのメリクロンの重要品目であるシニュアタは、1980年代までは実生固定種が栽培の大半を占めていました。ミヨシでは1988年に実生系の「シルキーミックス」に加えて、初のメリクロン品種である「ラメール」他3品種、1990年には実生系の「サンデーミックス」、メリクロン品種の「サンデーライトブルー」と「サンデーピンク」を発売、実生系とメリクロン系の両方の商品化を加速させました。これ以降は他社とのメリクロン品種の開発競争が強まりますが、「サンデーラベンダー」や「サンデーバイオレット」が国内定番品種としての地位を確立します。特に「サンデーバイオレット」は1999年に販売を開始した品種にも関わらず、永く国内流通切花本数のトップの座を占める不動の定番品種となりました。

リモニウムの新分野、ニューハイブリッド系
1997年には、後にニューハイブリッド系またはハイブリッドシネンシス系と呼ばれる品種群の先駆けとして、「サマーチェリー」「サマーイエロー」を販売開始。この品種群は元来、低温要求量が多い二年草ですが、低温要求量の少ない、二番花以降の採花が可能な品種の開発を進めました。「エバースノー」は南米市場においては年間50万本が作付けされる白の定番品種として定着しています。この品種群ではヒルベルダフローリスト社のダイヤモンドシリーズが多くの品種を揃えていますが、ミヨシ育種の「ブリスシリーズ」も徐々に販売数を伸ばしています。
シニュアタ発展のもう一つの要素、育苗体制
実生系シニュアタの高冷地育苗による暖地促成向け苗の生産販売が始まったのは1986年前後です。ミヨシでは、1985年に開場したティ・エム・ボール研究所栃木農場で生産された苗を本格的に販売開始しました。同農場は標高1,200mの高地にあり、育苗施設として、移動ベンチシステムや夜冷クーラー設備を備え、プラグトレイで15,000枚以上を生産することができました。サンデーミックスやシルキーミックスを中心に、288穴プラグに播種育苗した小苗を冷蔵庫で春化処理を行った後に、112穴・72穴や7.5cmポットに鉢上げして育苗した苗を出荷規格としました。これにより従来は生産者自身が行っていた冷蔵庫やクーラーハウスでの春化処理が不要となり、産地の大規模化に繋がるきっかけになりました。

安定生産に向けた取組み
実生品種に替わってメリクロン品種の販売量が増えるにつれて「変異」の問題がクローズアップされてきました。問題は90年代初頭には宿根性スターチスで認識され、続いてシニュアタでも発生が見られ始めました。株全体の矮化、草丈のバラつき、花序や葉型の異常形態などの症状が現れ、正常な切花が採れないことで生産者の収益に大きな損失を与えてしまいます。シニュアタにおいては特にピンク系の品種でリスクが高いことが、ミヨシ以外の会社の事例を含めて経験的に知られており、「ピンク系は1品種で10万本売ったら危ない」と言われていました。この問題を回避するために、組織培養技術の利点の享受と、意図しない形質をもった苗の発生・増加リスクを抑える手法の両立を目指す取り組みが始まり、現在もその努力を続けることで性質の安定化を図っています。

